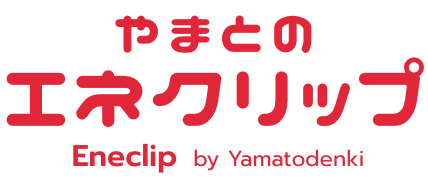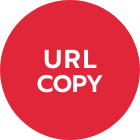持続可能な未来へ!「30by30」を理解しよう
「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」という言葉はあまり知られていないかもしれません。でも地球にはさまざまな生き物いて、それぞれがつながって生きていることを指す「生物多様性」という言葉は、多くの人が聞いたことがあるのではないでしょうか。いま地球は、気候変動や海洋汚染などによって、生物多様性が失われる危機に直面しています。
この生物多様性を守るための世界共通の目標が「30by30」です。今回は「30by30」の概要と取り組み事例をご紹介します。
「30by30(サーティ・バイ・サーティ)目標」とは、2030年までに、 陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標です。
引用元:環境省「30by30」特設サイト

目次
「30by30」の歩みと世界の動き
地球の生態系サービスは、今も失われ続けています。干ばつや氷河融解といった世界のニュースだけでなく、日本でも毎年のように最高気温が更新されたり、大雨の災害が増えていることからも実際に感じることができますね。こうした状況の中、生物多様性の損失を止め、元の良い状態に近づける「ネイチャーポジティブ」実現が世界的に強く求められるようになりました。その流れの中で、国際的な議論が進み、「30by30」目標が策定されました。以下では、「30by30」に関する重要な出来事を年代順に紹介します。
●2021年
G7サミットにおいて、G7各国は自国での「30by30」目標を約束
●2022年
COP15(生物多様性条約第15回締約国会議)で「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を採択。2030年グローバルターゲットの1つに
●2023年
日本政府は新たな生物多様性国家戦略「生物多様性国家戦略2023-2030」 を閣議決定
現在は「30by30」達成のための取り組みが本格的に動き始めた段階であることがわかります。次は日本の現状と取り組みを見ていきましょう。

日本の取り組み「自然共生サイト」とは?
日本でも「30by30」目標達成のための取り組みが始まっています。企業や自治体などの民間の協力が重要な鍵となります。
現在、国が管理する国立公園などの保護地域は、陸域で20.5%、海域で13.3%(2021年の調査結果)と、目標の30%にはまだまだ大きな差があります。そこで、自治体や企業が管理する里地里山や水源の森などを、国が「自然共生サイト」として認定する新たな取り組みを2023年に開始しました。

国と民間が一緒に力をあわせて、目標の30%まで持っていこうということですね。
自然共生サイトに認定されると、30by30目標達成に直接貢献できるだけでなく、一般消費者や投資家へのPRにも、企業価値やブランド力の向上にも役立ちます。
2025年4月からは、自然共生サイトを法制化した地域生物多様性増進法が施行されます。申請を希望する場合は、受付開始時期などの詳細を環境省の特設サイトで定期的に確認がおすすめです。

自然共生サイトをもっと身近に。自分ごとで捉えよう
目標達成には、国民一人ひとりの理解と積極的な取り組みが重要です。まずは、自分の地域でどのような取り組みが行われているかを知ることも大切な一歩。2023年から2024年前期にかけて、認定された自然共生サイトは通算253か所。そのうち、やまとの本拠地である鹿児島では4サイトが確認できました。
アマミノクロウサギ・トラスト 3 号地
【場所・面積】大島郡龍郷町、1.7ha
【申請者】(公社)日本ナショナル・トラスト協会
奄美大島 真米(まぐむ)の里 秋名・幾里・大勝
【場所・面積】大島郡龍郷町、1.3ha
【申請者】(一社) 奄美稲作保存会
山川の海のゆりかご
【場所・面積】指宿市、16ha
【申請者】山川町漁業協同組合
瀬戸内町 ネリヤカナヤの海
【場所・面積】大島郡瀬戸内町、49ha
【申請者】瀬戸内漁業協同組合、瀬戸内町
30by30達成のために、私たち個人でもできることはたくさんあります。例えば、環境に配慮した商品を選んで買う、省エネに取り組む、里山整備活動やゴミ拾いに参加する、生物多様性や環境保全に取り組むNPOに寄付することなどです。
地域や企業、そして私たち一人ひとりが力を合わせて、オールジャパンで取り組んでいくことが大切です。