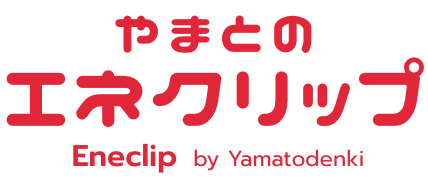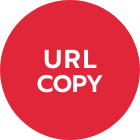知る、学ぶ。自家消費型太陽光発電と
「PPA」「PPAモデル」
太陽光発電の導入を検討していると、「PPA」や「PPAモデル」という言葉に出合うかと思います。今回はこの2つの違いと、自家消費型太陽光発電との関わりについて解説します。

目次
「PPA」と「PPAモデル」は何がちがう? 主流は?
【PPA】とは?
PPAは「Power Purchase Agreement」の略で、売電事業者と需要家が直接、電気の売買契約を結ぶこと。これにより需要家は「再生可能エネルギーの指名買い」ができるようになり、「100%太陽光発電由来の電気」を称することができます。
【PPAモデル】とは?
電力の需要家が敷地や屋根などのスペースを提供し、そこにPPA事業者が太陽光発電システムなどの発電設備を無償で設置、需要家は発電した電力を自家消費し、その分の電気料金をPPA事業者へ支払うという仕組みのこと。
今の日本では、電力の供給のインフラや法制度などの問題で、本来の「PPA」は実現がむずかしいというのが現状なようです。そこで需要家が選択できるのは「PPAモデル」のみとなり、主流は「PPAモデル」ということになります。
「PPAモデル」を導入するメリット

①初期投資・管理コスト0(ゼロ)
太陽光発電の設備および設置費用はPPA事業者が負担するのが通常です。また、契約期間中のメンテナンスもPPA事業者が行いますので、需要家は初期投資も管理コストもかかりません。大きな初期投資が必要な太陽光発電設備設置において、小さなコストでスタートできるのは最大のメリットです。
②事務負担0(ゼロ)
設置した太陽光発電の所有者はPPA事業者。なので、需要家は資産計上や減価償却など経理事務の手間も発生しません。

日常で変わるのは、電気代の支払先だけ!
③環境貢献、RE100加盟・SDGs達成の後押しに
発電・消費する電力は、CO2排出量が少ない自然由来の再生可能エネルギー。RE100に加盟するための条件達成のためや、SDGsの目標達成に貢献しているアピール材料として、十分に活用できます。

「RE100」や「SDGs」についても記事を書いていますので、ぜひお読みください!
「RE100」。”>「RE100」についてはこちらの記事をご覧ください
「SDGs」とは”>「SDGs」についてはこちらの記事をご覧ください
④契約満了後は設備が譲渡される
譲渡条件は事業者へ事前によく確認する必要がありますが、一般的には発電設備は契約満了後に無償で譲渡されることがほとんどです。契約満了後も発電した電気を、引き続き自家消費に利用できます。
PPAモデル導入のための施工業者の選び方
もし自家消費型太陽光発電を検討中で、PPAモデルを導入したいという方は、施工業者選びは慎重に。一般的にPPAモデルは契約が10年以上と長期間になることがほとんどです。契約満了後も安心して長期発電を行うためにも、契約期間中はもちろん、その後の“メンテナンスまでしっかり行ってくれるか?”“実績はあるか?”“透明性の高い長期のシミュレーションを出してくれるか?”に注意して施工業者をお選びください。
今回は、脱炭素社会に向けた活動が活発な今、今後も拡大が見込まれる「PPAモデル」について解説しました。次回はさらにもう一歩進んだ「オンサイトPPA」「オフサイトPPA」について深掘りしていきたいと思います。

ぜひ一緒に学びをふかめていきましょう。
それでは、また次回!
人気記事ランキング
知る、学ぶ。
「オンサイトPPA」と「オフサイトPPA」の違い
2022年日本のSDGs達成度は19位!これからの課題は?
2030年、100%LED化が政府の目標。照明の転換期を迎えています
知る、学ぶ。
「原子力発電」
知る、学ぶ。
「水力発電」
ちゃんと理解できている? 太陽光発電のメンテナンス義務化とは?
卒FIT前に届く買取期間満了通知は
必読! 要保管! の重要書類
工事なしでは発火のおそれも。LED化の注意点
知る、学ぶ。「グリーン電力証書・Jクレジット・非化石証書」とは?
実験レポート・太陽光発電設備の自立運転中にどのくらいの家電が使えるか
知ってなっとく!
これからのエネルギーのお話
JAPAN BUILD TOKYO 出展レポート
最新報告『日本の気候変動2025』を読み解く【前編】――2℃と4℃、未来を分ける2つのシナリオ
【2025年最新版】蛍光灯の終わり、LED照明の新常識
最新!エネルギー白書2025 日本のエネルギー最前線
電気・ガス料金支援、2025年夏も実施へ
ペットボトル1本から見る「カーボンフットプリント」
これからの太陽光発電はペラペラ!? 「ペロブスカイト太陽電池」
中小企業が脱炭素化に取り組むメリット